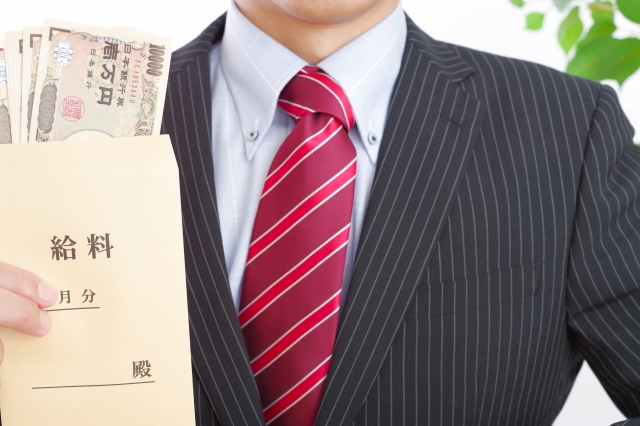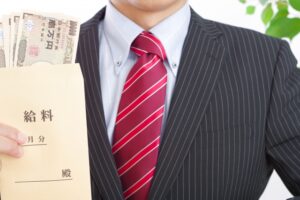会社を経営していると、「役員報酬(役員給与)」の取り扱いは避けて通れないテーマです。一般の従業員給与とは異なるルールが多く、税務上の制限もあります。間違えると損金不算入(経費として認められない)となり、法人税が増える可能性も…。今回は、役員給与の基本・労災保険の特別加入・法人税法上の注意点・源泉徴収のポイントまで、経営者や総務担当者が押さえておくべき内容をわかりやすく解説します。
1. 役員給与の基本ルール
役員に対する給与は、原則として所得税・住民税の課税対象です。さらに、健康保険や厚生年金保険にも加入します。しかし、ここで重要なのは労災保険や雇用保険は通常対象外という点です。
- 健康保険・厚生年金保険 → 加入対象
- 雇用保険・労災保険 → 原則対象外(例外あり)
なぜかというと、労災や雇用保険は「労働者」を保護する制度であり、経営者(役員)は会社を経営する立場だからです。ただし、次のようなケースでは例外があります。
2. 労災保険の特別加入制度とは?
経営者や個人事業主でも、現場で作業を行うなど「労働者に近い実態」がある場合は、労災保険の特別加入制度を利用できます。
特別加入が認められるケース
- 中小企業の役員や事業主が、現場で作業している場合
- 一人親方、個人事業主で危険を伴う業務に従事している場合
加入するためには、労働保険事務組合を通じて手続きするのが一般的です。特別加入をしておくことで、万一の業務災害に備えられるため、現場作業を伴う経営者は検討すべき制度です。
3. 法人税法上の取り扱い(損金算入できる?)
ここが最も重要なポイントです。役員への給与は、従業員給与と違って一部制限があります。
従業員の給与や賞与は、原則として経費(損金)に算入できます。しかし、役員の場合、損金にできるのは一定の条件を満たしたものだけです。
損金算入できる役員給与の種類
- 定期同額給与(役員報酬)
- 毎月同額で支給される報酬
- 支給時期が1か月ごと、支給額が同じであることが条件
- 増減する場合は、定期株主総会で決定が必要
- 事前確定届出給与(役員賞与)
- あらかじめ「支給時期・金額」を税務署に届け出たボーナス
- 株主総会終了後、1か月以内に税務署へ届け出必須
- 業績連動給与
- 利益などの業績指標に基づき計算される給与
- 非同族会社(オーナー会社以外)に限定
損金不算入となるケース(要注意!)
- 株主総会で決定せずに役員報酬を増額した場合
- 事前確定届出をしていない役員賞与
- 届出額と実際の支給額が異なる役員賞与
- 役員の私的な支出を会社が負担している場合
- 実際に働いていないのに給与を支払っている場合
ポイント: 税務署は「役員給与の不正」を厳しく見ています。届出忘れや変更のタイミングミスは命取りになるので、総務担当者は要チェックです。
4. 源泉徴収の取り扱い
役員給与や賞与も、一般の給与と同様に源泉所得税を天引きします。ただし、次の点に注意が必要です。
- 未払いの役員賞与は源泉徴収不要(支払い時に徴収)
- ただし、「支払日から1年を経過した日」までに未払いの場合、支払いがあったものとみなされ課税対象になる
- 納付書に記載する際は、「役員賞与」は従業員賞与と別欄に記載する
まとめ:役員給与は「税務リスクの高い領域」
役員給与は、会社経営において非常に重要なテーマですが、税務上のルールを誤ると経費計上できないリスクがあります。特に注意すべきポイントは次の3つです。
- 役員報酬は「定期同額」で、変更時は株主総会の決議必須
- 役員賞与は「事前確定届出」が必要。届出期限は株主総会終了後1か月以内
- 源泉徴収や納付書の記載も一般従業員とは異なる点あり
ワンポイントアドバイス:
役員給与の設計をする際は、税理士と必ず相談しながら進めることをおすすめします。とくに、賞与や増額のタイミングを誤ると、法人税が大きく増える可能性があります。
参考になる本としては、以下の書籍は図解も多くておすすめです。