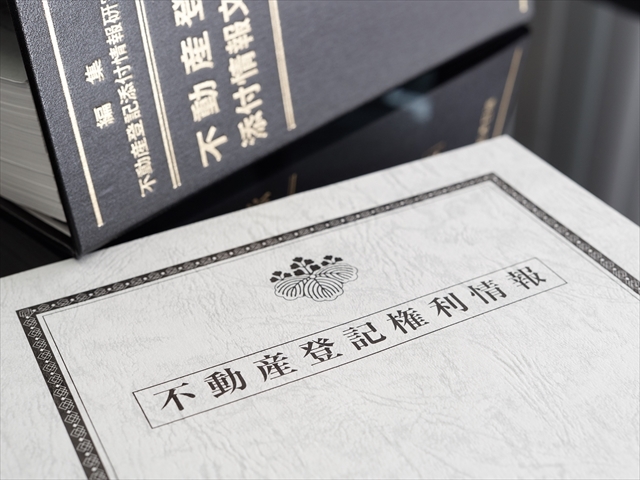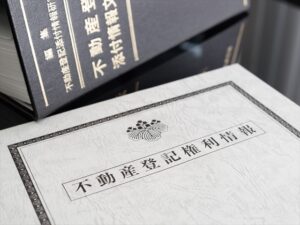1:調査の目的と進め方
物件調査は、不動産売買の現場で最も重要な業務のひとつです。売買契約書や重要事項説明書を作成するためには、正確で信頼できる情報を集める必要があります。その情報収集は、主に以下の3段階に分かれます:
ネットでの事前調査
現地での目視確認
役所での公式確認
この順番で進めると、効率的に必要な情報が集まります。
2:ネットでできる事前調査
① 登記事項証明書の取得(登記情報)
不動産の基礎情報である「登記事項証明書(登記簿)」は、最初に取得すべき資料です。今では【登記情報提供サービス】というオンラインサイトを使って、オフィスからPDFで取得可能です。
取得する書類:
土地全部事項
建物全部事項
公図
建物図面(各階平面図)
地積測量図
前面道路の土地全部事項、隣地土地の要約書
費用の目安:全部そろえて約2,000〜3,000円程度
※共同担保目録の表示は「あり」に設定して取得しましょう。
② 登記内容の見方
登記簿は「物件の履歴書」です。以下のように読み解きましょう:
表題部:地番、面積、建物構造など。重要事項説明書に反映されます。
権利部(甲区):所有権の変遷。相続や売買の履歴が分かります。
権利部(乙区):抵当権やその他の権利。ローン残債の推定に役立ちます。
読み取りポイント:
所有者の変遷 → 相続物件か、売却理由の仮説が立てられる
抵当権の有無 → 値引き交渉の余地があるか判断
抹消済の抵当権は下線付きで表示
③ 用途地域の確認
用途地域とは「その土地にどんな建物が建てられるか」を決めるルールです。ネットで「◯◯市 用途地域」などと検索すると、都市計画図のページが見つかります。
取得できる情報:
用途地域名(例:第一種低層住居専用地域など)
建ぺい率、容積率
防火・準防火地域
日影・斜線制限
市街化区域 or 市街化調整区域
これらは全て、販売資料や重要事項説明書に記載が必要な情報です。
④ 道路に関する情報
ネットでは「◯◯市 道路種別」「◯◯市 建築基準法道路」などで検索しましょう。
重要なのは、その物件が建築基準法上の「道路(幅4m以上)」に間口2m以上接しているかどうか。接していないと建築できない場合があり、大きなトラブルの元になります。
特に押さえるべき道路種別:
42条1項1号道路:一般的な公道(建築可)
42条1項5号道路:位置指定道路(役所にて確認が必要)
42条2項道路(二項道路):幅員4m未満でも、セットバックで建築可
43条2項2号道路:再建築には特別な許可が必要。原則避ける
⑤ ライフラインの調査(ガス・上下水道)
ガス:都市ガスの配管が前面道路にあるかを確認。配管図は大手ガス会社のサイトから申請可能。設置状況や共有配管の有無も要チェック。
上水道:事前手続き後、水道局で確認。配管の口径、引込の可否、距離と深さなど、将来的な費用見積りに関係します。
下水道:多くの市町村でネットから閲覧可能。合流式・分流式の違いや、浄化槽の有無・メンテ費用も調査対象です。
3:現地での確認ポイント
ネットや役所での調査とあわせて、現地確認も重要です。
現地でチェックすべき項目:
建物・設備の状況(劣化、破損など)
管理状態(共有部分の清掃など)
周辺環境(騒音、隣地とのトラブルの兆候)
境界標の有無
前面道路の幅員・舗装状況
現地では五感を使って「物件の空気感」も掴んでおきましょう。
4:役所での調査が必要な項目
最後に、どうしても役所に行かなければ確認できない情報があります。
道路種別の公式確認(口頭確認や図面取得)
都市計画、開発計画の将来情報
建築確認申請書(台帳記載事項証明書)
評価証明書(固定資産税の計算根拠)
ネットで調査した内容の裏付けを取る意味でも、役所調査は重要です。
より詳しい役所調査の進め方と実務ポイントは以下のボタンから、併せてご確認ください。
5:まとめ
1年目の営業として最初に覚えるべきことは「正確な情報を正しい手順で取得すること」です。
情報収集は「ネット → 現地 → 役所」の順
取得資料はPDF保存・印刷してファイリング
登記情報や用途地域は“読む”だけでなく“解釈”して付加価値を伝える
道路とライフラインは“建築の可否”や“追加費用”に直結
このマニュアルを何度も読み返して、実務を通じて理解を深めていきましょう。